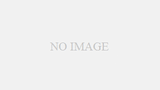はじめに:家づくりの“学び時間”が必要だと痛感
週末のある日、私は電話を手に取って、以前見学した建売住宅の営業担当へこう伝えました。
「すみません、今回は見送らせてください。」
共働きで平日は仕事に追われ、週末も子どもの行事や家族の予定が入りがち。
家づくりの打ち合わせを思うように進められず、建売住宅も、土地探しも一度リセットすることにしました。
💬 妻
「また最初からやり直しって感じだね。でも焦って決めるのも怖いし。」
💬 私
「うん。せっかくだから、今のうちに“住宅の勉強”をしておこうと思う。」
そう、私はこの時から意識的に**「住宅リテラシー(=家づくりの知識・判断力)」**を身につけることを決意しました。
ここからが、私の“学び”の日々のスタートです。
住宅リテラシーとは何か?
「リテラシー」という言葉には、「読み書き能力」や「理解力」という意味があります。
つまり住宅リテラシーとは――
家づくりにおける正しい知識と判断力を持つこと。
言い換えると、「営業トークに流されず、自分の価値観で判断できる力」です。
💬 妻
「たしかに、どこのハウスメーカーも“今だけキャンペーン中です”とか言ってたね(笑)」
💬 私
「そうそう。あれも悪意があるわけじゃないけど、知識がないと判断できないんだよね。」
🔍 住宅リテラシーが低いと起こるリスク
- 広告の「価格」に惑わされる(実際はオプションだらけ)
- ローンの組み方を誤って家計を圧迫
- 土地と建物の優先順位を間違える
- “建てた後”の維持費を見落とす
家は「買う」ものではなく、「建てて、暮らしていく」もの。
知識の有無で、満足度も資産価値も大きく変わってくるのです。
週末に展示場へ行けないなら「勉強時間」に変える
共働き夫婦にとって、**家づくりの最大の課題は「時間」**です。
私たちも例外ではなく、週末は子どもの習い事や買い物、家事で埋まってしまい、住宅展示場に行けない週が続きました。
しかし、ただ時間を無駄にするのはもったいない。
そこで私は、「学ぶ時間」にシフトすることにしたのです。
私が実際に読んでよかった住宅関連書籍3選
📘 ①『後悔しない家づくりの教科書』(著:さくら事務所)
住宅診断(ホームインスペクション)で有名な「さくら事務所」の代表が書いた本。
実際の失敗事例を交えながら、「建てる前に知っておくべきポイント」が網羅されています。
「デザインより“断熱性能”を優先すべき理由」や
「坪単価のカラクリ」など、営業マンが言わない話が多くて勉強になります。
📘 ②『トクする家づくり損する家づくり』(著:滝沢俊之)
累計50万部超の定番書。
資金計画・土地選び・間取りづくりまで、家づくりの全体像を理解できます。
「家づくりは“ゴール”ではなく、“スタート”」という言葉が印象的でした。
📘 ③『建築知識ビルダーズ』(雑誌)
専門誌ですが、図解や施工写真が豊富でわかりやすいです。
「ZEH住宅」「耐震等級3」「断熱等級6」など、最近の住宅性能トレンドを掴むには最適。
💬 妻
「私は“間取りの本”が好き。インスタで見たおしゃれな家の実例もチェックしてるよ。」
💬 私
「それも大事だね。見た目と性能のバランスを考えたい。」
YouTubeで学ぶ住宅知識(おすすめチャンネル5選)
書籍だけでなく、最近はYouTubeでも質の高い住宅情報が手軽に得られます。
私が特に役立ったチャンネルを紹介します。
🎥 ①「もりけんチャンネル」
元ハウスメーカー営業の森健さんが、営業トークの裏側やハウスメーカーの選び方を丁寧に解説。
「営業マンの口車に乗せられない力」がつきます。
🎥 ②「ラクジュ建築と不動産」
一級建築士の山本さんが、設計・間取り・構造について詳しく説明。
「なぜこの間取りが住みやすいのか」を理論で理解できます。
🎥 ③「家づくり百貨」
全国の工務店が集まって運営するチャンネル。
動画で実際の施工例や失敗談を紹介しており、工務店のリアルな視点を学べます。
🎥 ④「SUUMO公式チャンネル」
基礎的な知識を知りたい人に最適。
ローン・土地選び・相場感などをわかりやすくまとめています。
🎥 ⑤「ヒラヤスタイル」
平屋に特化した住宅系YouTuber。
“間取りの失敗しないコツ”や“平屋の光熱費”など、実生活に即した情報が魅力。
💬 妻
「夜、子どもが寝たあとにYouTube流してたのは、勉強してたのね。」
💬 私
「そう(笑)。寝る前の30分を“住宅勉強時間”にしてたんだ。」
住宅展示場に行く前に“基礎知識”をつけておく
展示場に行くと、どのモデルハウスも魅力的に見えます。
しかし、リテラシーが低いと――
「モデルハウスの標準仕様=自分の家にできる仕様」
と勘違いしてしまう。
この誤解が、家づくり失敗の第一歩です。
💬 妻
「展示場の家って、全部すごく立派だったよね。吹き抜けに大理石の床とか。」
💬 私
「あれは“見せるための家”だから。実際に建てるときは標準仕様を確認しないと。」
展示場を見に行く前に、基本的な住宅性能・コスト構造を理解しておくと、
営業担当の話を冷静に判断できます。
住宅リテラシーを高める3つのステップ
ここで、私が実践して効果を感じた「住宅リテラシー向上法」を整理します。
STEP1:信頼できる情報源を選ぶ
→ 書籍・YouTube・専門家の発信を軸にする。SNSの断片的な情報に振り回されない。
STEP2:知識を自分の状況に当てはめて考える
→ 「自分たちの予算・生活スタイルに合うか?」を常に意識。
STEP3:夫婦で共有する
→ どちらか片方だけが詳しくなると、意思決定がスムーズにいかない。
“夫婦のリテラシー格差”を埋めるのも大切です。
💬 妻
「勉強し始めたら、住宅会社の広告の“からくり”がわかるようになった気がする。」
💬 私
「それが住宅リテラシーだね。『安い理由』『高い理由』を説明できるかがポイント。」
情報を得たことで、家づくりの方向性が見えた
勉強を重ねるうちに、私の中で次第に方向性が定まってきました。
- 自分たちに合うのは注文住宅
- 性能とデザインのバランスを重視したい
- 無理のない資金計画を立てたい
つまり、**「焦らず、納得のいく家づくりをしたい」**という結論です。
まとめ:住宅リテラシーが未来の満足度を決める
振り返ってみると、家づくりを“止めていた時間”は、
決してムダではありませんでした。
むしろ、住宅リテラシーを高める最高の期間だったと思います。
💬 私
「これからは、知識をもって展示場やハウスメーカーと話ができるね。」
💬 妻
「うん、なんだか自信がついた!今度こそ、納得できる家づくりにしよう。」
次回予告
次回は――
「#10 注文住宅は土地探しが先?ハウスメーカー・工務店が先?」
多くの人が迷う“家づくりの順番”について、実体験を交えながら解説します。
お楽しみに!